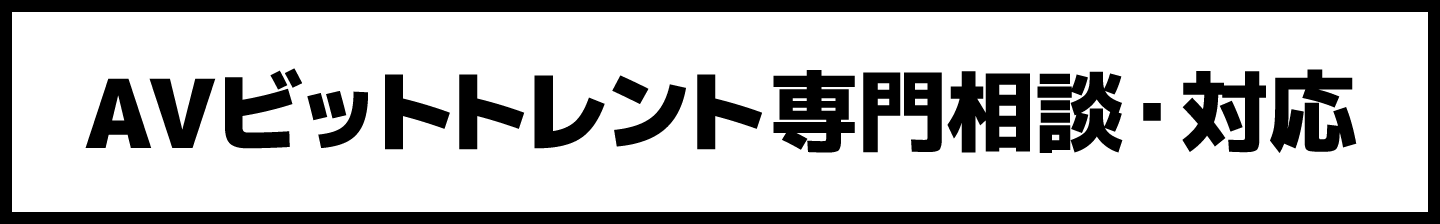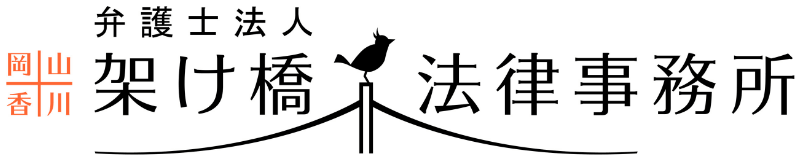この記事を書いた弁護士
代表弁護士 呉 裕麻(おー ゆうま)
出身:東京 出身大学:早稲田大学
2008年に弁護士登録後、消費者案件(出会い系サイト、占いサイト、ロマンス詐欺その他)、負債処理(過払い、債務整理、破産、民事再生)、男女問題(離婚、不倫その他)、遺言・遺産争い、交通事故(被害者、加害者)、刑事事件、インターネットトラブル(誹謗中傷、トレント、その他)、子どもの権利(いじめ問題、学校トラブル)、企業案件(顧問契約など)に注力してきた。
他にも、障害者の権利を巡る弁護団事件、住民訴訟など弁護団事件も多数担当している。
1 民事訴訟に発展するケース
制作会社からの示談交渉に対し、示談に応じない場合には、制作会社としては発信者に対する責任追及を実現するため、法的手段を検討することになります。
そこで、制作会社は発信者を被告として民事裁判を起こすケースがあります。
民事裁判を起こされるケースとしては、「ダウンロード回数(ダウンロードやアップロードを行った発信時刻からアップロードを停止したと推測される日(例えば、受任通知を作成した日、もしくは、開示を受けた日)までの期間の間で他のトレントユーザーがダウンロードした回数)」×「当該作品の利益額」を損害として数百万円程度の請求を行うケースがあります。
もっとも、当事務所で取り扱ってきた案件やクライアントで民事裁判を起されたケースは、現状ごくわずかに留まっています。
民事裁判を起こす制作会社も少数に留まりますが、民事裁判に至った場合には適切に対応する必要があります。
なぜなら、トレントの利用状況等によっては、制作会社が請求する金額が実際の損害額として相当とはいえない場合もあり、適切な損害額での解決を図るためには、適切に主張反論、証拠の提出を行う必要性が高いからです。
2 民事訴訟での手続きと対応について
民事訴訟では、互いに主張内容を記載した準備書面、根拠となる証拠を提出しなければなりません。
よくある流れとしては、次回期日までにこちらの主張反論の書面を提出し、次回期日ではそれを踏まえて期日に臨みます。
そして、次々回期日までに次は相手方が反論準備を行うことになり、それを当事者で交互に主張反論を繰り返していきます。
さらに、裁判所は当事者の主張や証拠を基に、請求の根拠があるのか、請求の根拠があるとしてその損害額がどの程度かを判断します。
この点、発信者側としては、その請求の根拠があるかどうか、生じた損害額について的確に主張反論、証拠の提出を行う必要があります。
例えば、発信者が当該作品をダウンロードやアップロードをしていた前提で、ダウンロードが完了した後すぐにトレントファイルを削除しアップロードがされないようにしていたケースでも、制作会社は発信者がアップロードを停止した以降に生じた損害についても請求を行う場合がほとんどです。
民事訴訟においては、しばしば
①ユーザーが利用を停止した後の損害についても責任を負うか
②損害賠償を負うこととなる終期をどの時点に認定するか
が問題となります。
これらの問題に関して、裁判例をみると次のように判断しています。
⑴東京地方裁判所令和3年8月27日判決
②損害賠償を負うこととなる終期をどの時点に認定するか
弁護士に相談をした日
⑵知的財産高等裁判所令和4年4月20日判決(⑴判決の控訴審)
②損害賠償を負うこととなる終期をどの時点に認定するか
弁護士に相談した日もしくはユーザーがトレントファイルを削除し、もしくは利用を停止した日
⑶大阪地裁令和5年8月31日判決
②損害賠償を負うこととなる終期をどの時点に認定するか
トレントファイルを削除するまでの3時間
この点、①に関してはいずれの裁判例もユーザーが利用を停止した後に生じた損害の責任を否定しています。
他方、②に関して、⑴判例は、⑵、⑶判例と若干判断が異なっていますが、
「原告ら代理人からBitTorrentの利用を直ちに停止すべき旨の助言を受けたものと推認することができるから,同原告らは,それぞれ,遅くとも同日にはBitTorrentの利用を停止し,もって,本件各ファイルにつきアップロード可能な状態を終了したものと認めるのが相当である」
ことを理由として、裁判所が推認に基づき終了時期の事実認定を行っています。
一方、⑵判決と⑶判決はより直截に、ユーザーが陳述書で主張する利用停止時期や削除の時期をもって終期を素直に認定しており、⑴判決と比較して終期までの期間が短くなっています。
当事務所では、裁判例の考え方を踏まえ、当該発信者のトレント利用状況に応じて適切な損害額を主張する、必要な証拠を提出するなどの訴訟対応を行います。
こうした働きかけを通して、適切な損害額での解決の実現を図ります。
裁判所は、当事者の主張、立証がある程度出尽くした状況になると、和解を提案することがあります。
具体的には、裁判所が当該事案の具体的状況に照らして、和解案(解決金等の条件)を当事者に提案するケースも見られます。
この場合、当事者双方が和解案に納得すれば、和解での解決が可能です。
他方、当事者間で和解の意思がない場合や和解の条件で折り合いがつかない場合には、裁判所に判決を出してもらうことになります。
3 民事訴訟における弁護士の役割と必要性
当事務所では、トレント案件での民事訴訟対応において、これまでの訴訟対応の経験を踏まえ、戦略的なサポートを提供しています。
訴訟対応での弁護士の役割は、
①適切な損害額での解決を実現すること
②有効かつ適切な主張反論、証拠提出などの訴訟対応を行うこと
③期日への出頭などの負担を軽減すること
が挙げられます。
③に関しては、裁判期日での訴訟対応を弁護士に任せることができるため、ご依頼者様が裁判所に出頭する必要はありません。
また、民事訴訟では、法的構造などの専門的な知識が必要となるため、本人対応が難しい側面もあります。
加えて、示談交渉の場面と異なり、裁判所から訴状が届いたにもかかわらず何らの対応を行わない場合には、制作会社の請求が認められ、支払責任を負う危険性があります。
そのため、トレント事案での訴訟対応の経験を有した弁護士に依頼することが重要になります。
執筆者:弁護士 呉裕麻(おー ゆうま)
1979年 東京都生まれ
2002年 早稲田大学法学部卒業
2006年 司法試験合格
2008年 岡山弁護士会に登録
2013年 岡山県倉敷市に岡山中庄架け橋法律事務所開所
2015年 弁護士法人に組織変更
2022年 弁護士法人岡山香川架け橋法律事務所に商号変更
2022年 香川県高松市に香川オフィスを開所