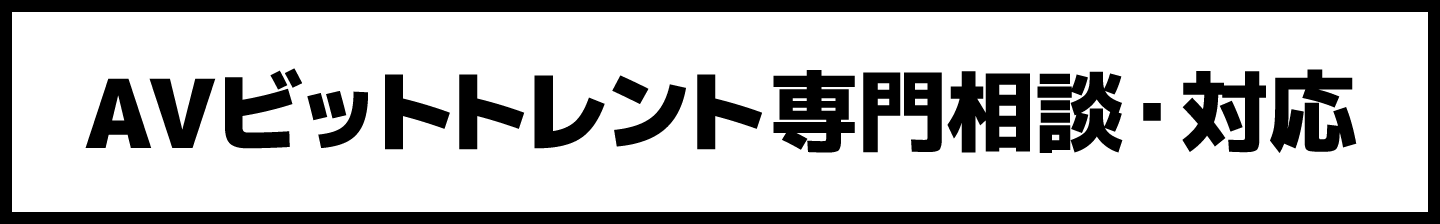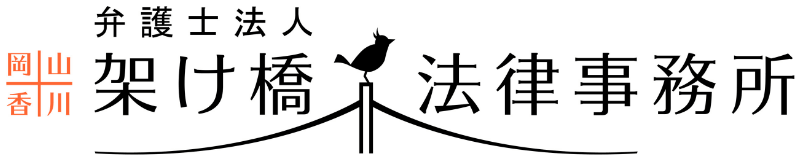この記事を書いた弁護士
代表弁護士 呉 裕麻(おー ゆうま)
出身:東京 出身大学:早稲田大学
2008年に弁護士登録後、消費者案件(出会い系サイト、占いサイト、ロマンス詐欺その他)、負債処理(過払い、債務整理、破産、民事再生)、男女問題(離婚、不倫その他)、遺言・遺産争い、交通事故(被害者、加害者)、刑事事件、インターネットトラブル(誹謗中傷、トレント、その他)、子どもの権利(いじめ問題、学校トラブル)、企業案件(顧問契約など)に注力してきた。
他にも、障害者の権利を巡る弁護団事件、住民訴訟など弁護団事件も多数担当している。
1意見照会書とは?
意見照会書とは、
ビットトレントシステム(BitTorrent)の利用に伴い、インターネットサービスプロバイダー(ISP)から送付される「発信者情報開示請求に伴う意見照会書」
のことです。
ここ数年、この意見照会書の受領に関する法律相談が急増しており、特にアダルトビデオの製作会社等からの開示請求を受けたプロバイダーからのものが最も多く見られます。
製作会社は自社の著作物に対する著作権を有しており、その権利が侵害されたとして、発信者情報開示請求を弁護士に依頼し、プロバイダーが契約名義人に対して意見照会書を発送しています。
また、製作会社は、著作権以外のパブリシティ権や肖像権などを根拠に発信者情報開示請求をしてくることもあります。
この意見照会書が届いたら、書面に記載のある回答期限までにプロバイダーに回答書を書いて提出する必要があります。
2意見照会書の前提となる開示請求の手法について
プロバイダーからの意見照会書は、製作会社の代理人弁護士からの発信者情報開示請求を前提としています。
そして、この発信者情報開示請求の手続きには二つのやり方があります。
一つは任意開示請求と呼ばれるものであり、裁判所を通じた法的強制力を伴わない、契約名義人からの同意を前提もしくはプロバイダーからの任意での開示を求めるものです。
この任意開示の場合には、多くは一般社団法人テレコムサービス協会の提供する書式(いわゆるテレサ式)を用いて行われることが多く、そのため、開示請求の書式を見ることでこの任意での開示請求か否かの判断が可能となっています。
そして、任意開示請求の場合には、意見照会書に不同意で回答をすると、プロバイダーは通常は発信者情報開示請求に応じないことから、個人情報は開示されずに終わることがあります。
ただし、プロバイダーによっては契約名義人からの不同意の回答にも関わらず、開示請求者からの書面の内容を前提にプロバイダーとしての判断に基づき開示をすることもあるので注意が必要です。
この任意開示請求とは別に、もう一つ、情報流通プラットフォーム対処法(旧プロバイダ責任制限法)に基づき裁判所に発信者情報開示請求命令申立てを行い、開示を求める方法があります。
この方法の場合には、仮に不同意で回答をしても、裁判所が開示理由を認めれば開示命令の発令となり、結果、プロバイダーは個人情報の開示に応じることとなります。
以上のように、開示請求の方法がいずれによるかによって回答書への対応方法も異なってきます。
そのため、当該意見照会がいずれの方法に基づく開示請求を前提としているかをきちんと確認することが重要です。
そして、その確認の方法としては、
① 意見照会書自体に、裁判所の名前や開示請求者から発信者情報開示命令が申し立てられたなどの説明が書いてあるか否か
② 裁判所提出書面(申立書や甲号証)の写しが同封されているか否か
③ テレサ書式による申立書が同封されているか否か
などによって判断することとなりますし、分かりにくい場合には直接プロバイダーに確認することもできます。
もしくは当事務所などトレント案件を取り扱う弁護士に尋ねていただいても構いません。
3意見照会書の回答内容について
意見照会書を受領した場合、最初に行うべきことは、「開示に同意で回答するか、不同意で回答するか」を決めることです。
以下、順番に解説します。
⑴ 不同意で回答する場合
そもそも自分自身ではビットトレントシステムの利用がないケース(例:自宅のWi-Fiを契約名義人以外の同居家族、友人、知人、あるいは隣家の住人が利用してアダルトビデオをダウンロードしたケース)では、「利用をしていないこと、使用していないこと」を理由に不同意で回答書を作成します。
また、ビットトレントシステムは利用したが、当該開示請求の対象となっているファイルに見覚えがない場合も、不同意で回答することがあります。
他にも、AV男優やAV女優からの開示請求の場合、パブリシティ権侵害や肖像権侵害などを根拠とする開示請求がされることがあります。
これらを理由とした開示請求は、現在裁判所が認めていないため、権利侵害の明白性が認められないとの理由にて、不同意で回答を出すのがセオリーです。
さらに、上記でも解説したように、任意開示の方法での意見照会の場合には、不同意で回答をすることで開示にならずに済むことがあります。
この点、トレントを利用したとの認識があったとしても、できれば不開示で終わりたいとの考えであれば不同意での回答書を作成し、提出することで開示にならずに済むのでそのような対応も検討の余地があります。
⑵同意で回答する場合
上記のような不同意のケース以外では、同意で回答することになります。
弁護士は、ご自身の置かれた状況を踏まえ、意見照会書に対するベストな対応を検討し、ご案内いたします。
ご依頼の際には、プロバイダーへの意見照会書の返答も弁護士事務所にて行います(ただし、回答期限が迫っている場合にはご本人から回答をしてもらうこともあります)。
回答書の提出を含め、お気軽にご依頼いただけたらと思います。
4意見照会書の回答期限について
意見照会書には、通常1週間ないし2週間という回答期限が設けられています。
突然、意見照会書を受け取り、その内容に驚き、さらには回答期限が短いことでとても慌てる方が多いです。
そのため、意見照会書を受け取ったらまずはご自身のおかれている状況をしっかりと確認し、できれば弁護士に相談の上で意見照会書の回答を期限内に行うことをお勧めします。
また、回答期限が気になる場合には、プロバイダーに対して回答期限の猶予を求めることもご検討ください。
プロバイダーによってはこれに応じるところがあります。
ただし、慌てて、「とにかくすぐにつながる相談先、弁護士」に安易な相談や依頼をすることは危険です。
トレントの分野では、一部、相談者の不安や焦りを緩和せず、単に早期の示談ばかりを勧める弁護士が存在します。
くれぐれも相談先の弁護士選定にはご注意ください。
とにかく、意見照会書を受領しても、
「慌てて結論を決めないこと」
が最も大切です。
即座に回答しないからといって逮捕されたり、すぐに裁判になったりすることはありませんのでご安心ください。
慌てて示談に応じることや、不安から
すぐに示談しないと大変なことになる
刑事告訴される
といった言説に惑わされないようご注意ください。
5意見照会書に回答しなかった場合
万が一、期限を徒過したとか、回答を忘れたなどの理由により、意見照会書に対する回答をしなかったからといって「同意をした」とみなされるわけではありません。
プロバイダ責任制限法ガイドライン等検討協議会によるガイドライン上では「開示に関して特段の主張を行わないもの」として扱われます。
これは同意をしたとみなすという意味にはなりませんのでご安心ください。
6意見照会書・開示請求への対応のまとめ
以上のとおり、プロバイダーからの意見照会書には、回答期限を踏まえて、過度に心配になったり慌てたりすることなく落ち着いて対応をすることが大切です。
ご不安がぬぐえない場合にはやはりこの分野に詳しい経験のある弁護士にご相談いただくことを強くお勧めします。
執筆者:弁護士 呉裕麻(おー ゆうま)
1979年 東京都生まれ
2002年 早稲田大学法学部卒業
2006年 司法試験合格
2008年 岡山弁護士会に登録
2013年 岡山県倉敷市に岡山中庄架け橋法律事務所開所
2015年 弁護士法人に組織変更
2022年 弁護士法人岡山香川架け橋法律事務所に商号変更
2022年 香川県高松市に香川オフィスを開所